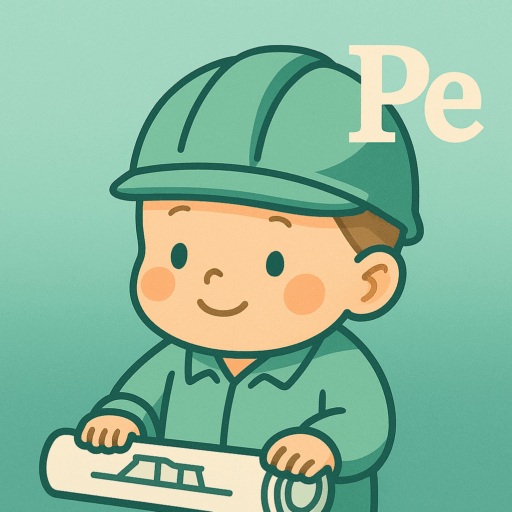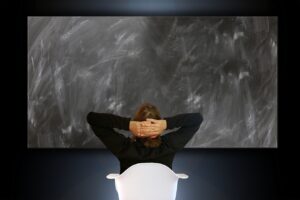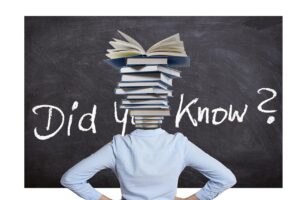こんにちは、赤ちゃん技術士です。
前回の記事でお伝えしたとおり、受験を決めたものの、正直なところ「さて、何から始めればいいんだ?」という気持ちでした。
そこで私は、いきなり問題を解くのではなく、まず技術士二次試験がどんな試験なのかをしっかり理解することから始めました。
これは「知識を答える試験」ではない
調べていくうちに、最初に気づいたのは、
この試験は、“どれだけ知識があるか、専門用語を知っているか”を問う試験ではない。
“技術者としての資質”=コンピテンシー(資質能力)を問う試験だ。
これまで経験してきた大学受験や資格試験とは異なる試験スタイルに、最初は少し戸惑いました。
特に重要なのは、各問題(Ⅰ、Ⅱ-1、Ⅱ-2、Ⅲ)で問われているコンピテンシーを正しく理解すること。
これは、受験申込案内に明記されていますので、必ず目を通しておきましょう。
コンピテンシーを意識せず、知識に偏重した論文を書いてしまうと、「専門的学識」の部分しか評価されず、点数が伸びにくくなります。
合格答案を「書き写す」ことで型を体得する
次に私が取り組んだのは、実際の合格者の答案をひたすら書き写すことです。
私はスキヤキ塾で販売されている合格論文のサンプルを購入し、内容を理解する前に、まずは一字一句、そのまま紙に書き写してみました。
…これが意外とキツい。
時間もかかるし、手も痛くなるし、集中力も削られます。
「これ、続けられるのかな…」と何度も思いました。
ですが、数回繰り返していくうちに、
- 「なるほど、こういう課題が出るのか」
- 「ここで“公益確保”に触れているな」
- 「論文って、こうやって構成するのか」
というように、答案の“型”が自然と身体に染み込んでくる感覚を持つようになりました。
ただ読むだけでは気づけなかった構成や言葉の流れ。
実際に手を動かすことで、筆者の意図や論理展開が体に入ってくるんです。
政策へのアンテナも大事
もう一つ始めたことがあります。
それが、国土交通省のメールマガジンに登録し、毎週届く政策情報に目を通すことです。
すべてを理解するのは正直難しいです。
ですが、
- 「今、国はどんな方向性を出しているのか?」
- 「繰り返し出てくるキーワードは何か?」
そういった視点で読むと、論文に使えるネタや表現が自然と目に入るようになってきました。
たとえば、「流域治水」や「防災DX」など、出題頻度の高いテーマに関する情報も、ここからキャッチできます。
今回は「書く前の準備」の話でした
今回お伝えしたのは、「論文を書く前の土台づくり」についてです。
- 試験の本質を理解する
- 合格答案の型を身体に覚えさせる
- 政策情報にアンテナを張る
どれも派手な方法ではありませんが、この地味な準備が、後々大きな差になると私は感じました。
次回は、論文の書き方や、実際に使った参考書についてご紹介する予定です。
引き続き、よろしくお願いします!