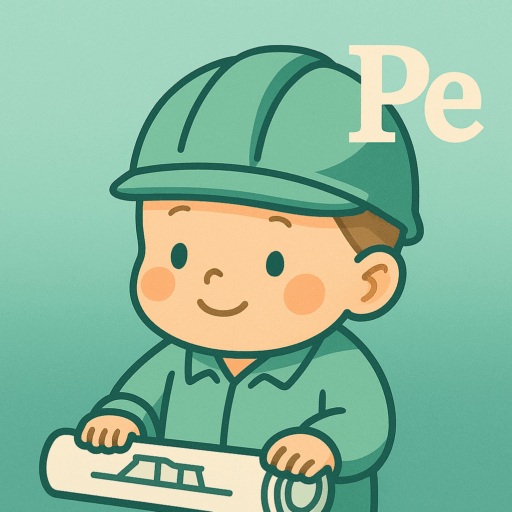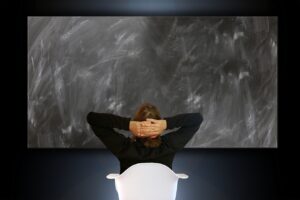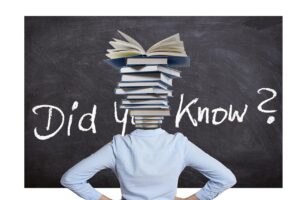技術士試験の勉強を始めたばかりの頃、「何から読めばいいのか」でつまずきました。
本屋に行けば本はたくさん並んでいるし、ネットでも情報は山ほど出てくる。
でも、どれが“本当に使える”のかがわからない。
そんな中で、実際に手を動かしながら試行錯誤を重ね、「これは使える!」と実感したものだけが、今も手元に残っています。
今回はその中から、「論文が書けるようになった」と心から感じた3つの情報源をご紹介します。
1. 『技術士第二次試験 建設部門 最新キーワード100』(日経BP)
技術士試験では、国土交通省の政策や最新技術動向の理解が欠かせません。
この本はそれらを「100のキーワード」でコンパクトに整理してくれていて、非常に読みやすく、かつ実用的です。
特に役立ったポイント:
- 国交省の政策や施策が体系的に整理されている
- 分厚い資料を読む代わりに、この1冊で要点がつかめる
- キーワード同士の関係性も見えてきて、俯瞰的な理解が進む
私はこの本をネタ帳のように使い、「このテーマなら、どのキーワードが関連しそうか?」といった視点で論点を広げていきました。
論文の“タネ”を探すのに、最も使った一冊です。
2. 『合格者の回答論文』(SUKIYAKI塾)
実際に試験当日に書かれた合格答案がまとめられている参考書です。
同じテーマでも、合格者によって切り口や展開がまったく異なっていて、視野が一気に広がりました。
印象的だったポイント:
- 合格者ごとの“視点の違い”がとても勉強になる
- 課題 → 解決策 → リスクの展開の流れが見えてくる
- 回答の方向性を比較することで、自分の論文の軸が定まる
私はこの本を、ただ読むだけでなく、回答をパーツに分解してストックしました。
たとえば、「課題」「対策」「リスク」などの項目ごとに整理しておき、それらを組み合わせながら、自分の論文の骨子を作るようにしていました。
3. X(旧Twitter)「J-Index」さんの添削投稿
最後は書籍ではなく、SNSで得たリアルな知見。
特に「J-Index」さんが投稿していた技術士論文の添削シリーズは、実践的な内容が多く、何度も見返しました。
活用してよかった点:
- 他の受験者のレベル感がわかって、良い意味で焦る(=モチベUP)
- 添削の指摘が具体的で、「悪い例」から学べる
- 自分では気づけない文章の“クセ”や“甘さ”を客観視できる
私は「上手な例」よりも「ダメな例」にこそ学びがあると思っていて、この添削投稿はまさに反面教師として大活躍でした。
また、1段落の文字数や構成バランスも参考にして、自分の文章にも取り入れました。
おわりに|「自分の論文が書けるようになった」と思えた3つの情報源
あれこれ手を出してきましたが、振り返ってみると「本当に力になった」のはこの3つだけでした。
- 政策理解のベースとして:『技術士第二次試験 建設部門 最新キーワード100』
- 論文構成の型を作るために:『合格者の回答論文』
- 実践的なブラッシュアップのために:Xの添削投稿
これから受験される方にとって、少しでも参考になれば嬉しいです。
次回の【第4話】では、「実際にどうやって論文を構成していったか?」という視点で、書き方の基本的なところについて紹介する予定です。
ぜひお楽しみに!