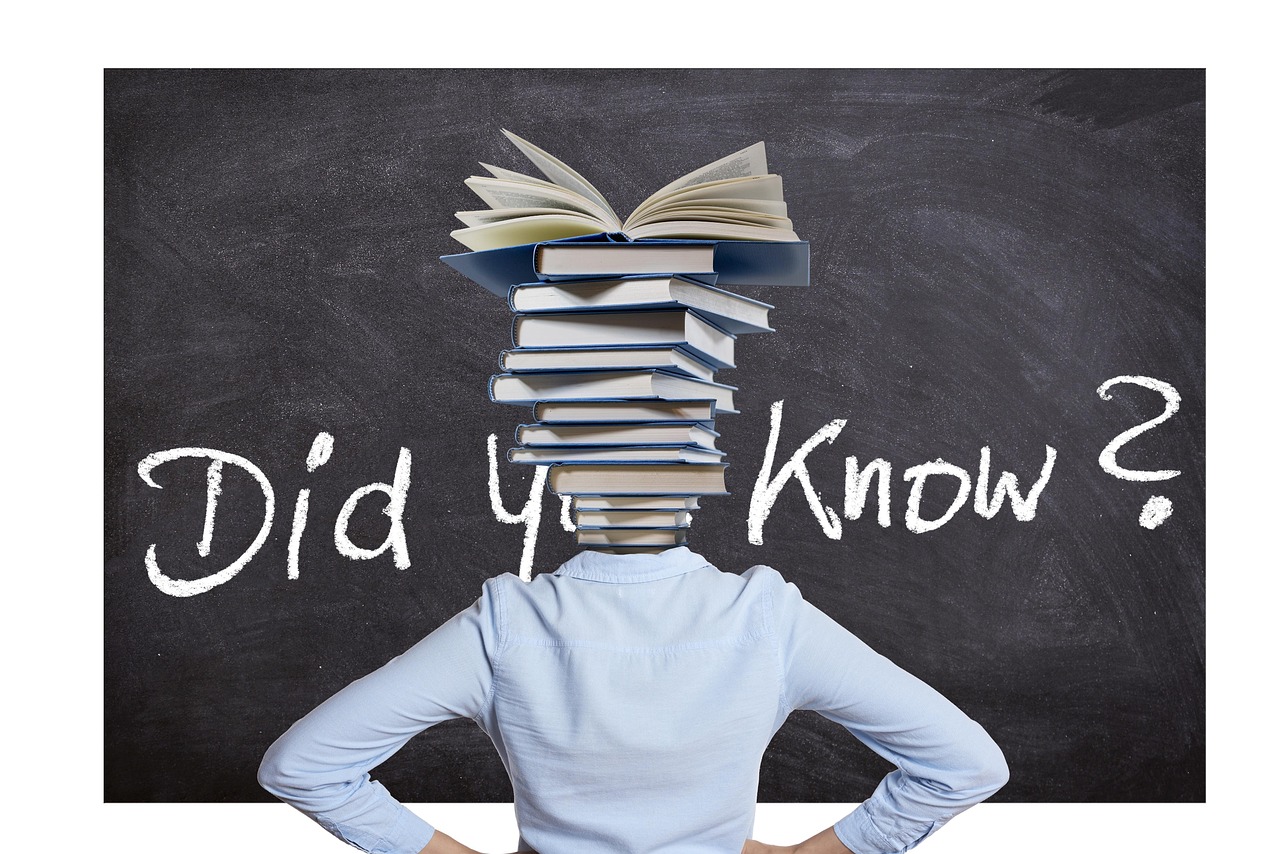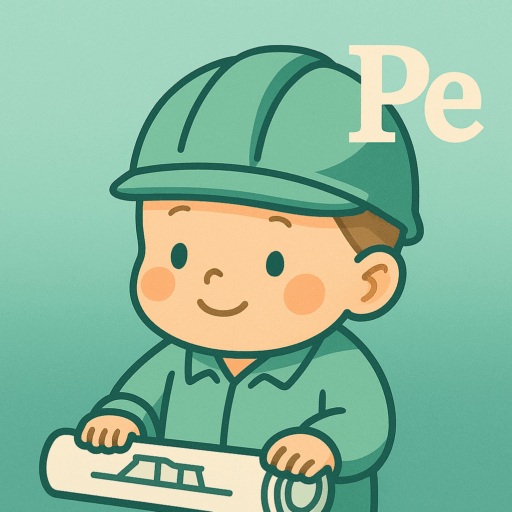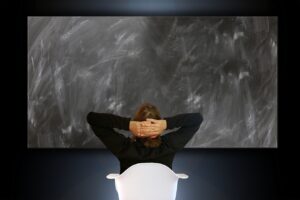技術士試験の論文対策を始めたばかりの頃、
「課題ってつまり“問題点”のことだよね?」
…そんなふうに思っていた私ですが、今振り返ると、これは大きな落とし穴でした。
論文対策において、「課題」という言葉をどう理解するかで、文章の深さも説得力も大きく変わってきます。
今回は、私が論文を書いていく中で実感した
「課題」の本当の意味と、似た言葉との違いについてまとめてみました。
論文における「課題」は、ただの“問題点”ではない
技術士試験で使われる「課題」という言葉。
なんとなく、「問題点」とか「改善点」と置き換えて考えている方も多いのではないでしょうか。
私もそうでした。
でも、実際に過去問や模範解答を読み込んでいく中で、「課題」の意味はもっと広くて深いものだと気づきました。
「課題」とは、目標達成のために解決すべきテーマのこと
「課題」とは、単なる“不具合”や“悪い点”ではなく、
「目標を達成するために解決すべきテーマ」のことです。
たとえば――
- 「流下能力が不足している」 → これは問題点
- 「どうすれば適切な流下能力を確保できるか」 → これが課題
このように、課題は“あるべき姿と現状とのギャップ”なんですね。
問題点に気づくだけでは不十分で、それにどう向き合うかまで踏み込む必要があります。
「課題」はポジティブなものになる
課題の抽出や設定をする上で、明らかに間違えていないか確認できる方法があります。
それは、「課題」がポジティブなものになっているか確認するということです。
一方で「問題点」は、課題を解決する上で障壁になっているものなので、ネガティブな要素になります。
- 「持続可能な流下能力の確保」 → 課題(ポジティブ)
- 「樹林化による河積阻害」 → 問題点(ネガティブ)
論文を書くときは、課題と問題点を明確に使い分けられなければいけません。
課題の抽出に迷ったら、ポジティブな表現になっているかを意識してみることが大切です。
「課題の解像度」が上がると、論文が変わる
課題の意味がクリアになると、論文全体がぐっと書きやすくなります。
私が実践していたことは以下の通りです:
- 合格者の回答論文の「課題」をすべて抜き出して比較(スキヤキ塾で購入)
- 模範論文の「課題」と「解決策」のつながりを分析
- 日常業務でも、課題と問題点を整理しながら考えてみる
こうして「課題の引き出し」を増やしていくことで、文章の軸がしっかりし、論理的な構成ができるようになりました。
まとめ:課題という言葉を明確に理解することが、合格への一歩になる
技術士試験の論文は、「技術を社会にどう活かすか」を言葉で伝える試験です。
だからこそ、「課題」「問題点」などの言葉を正しく理解し、適切に使い分ける力が問われます。
私は「課題って何?」を突き詰めて考えることで、
論文の説得力が大きく変わったと実感しています。
以上が、私が論文対策を始めた時に大切にしていたことです。
読んでいただき、ありがとうございました!